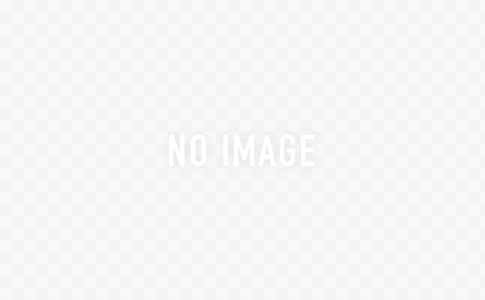<追記>下記記事内容に関しまして、解説動画を作成いたしました。
本書P241の内容につきまして、JIS規格の変更に伴い修正が発生しています。読者の皆様にはご不便をおかけし申し訳ありませんが、下記ご確認願います。
本書P241→光ファイバの接続に光コネクタを使用したときの挿入損失を測定する試験方法は、光コネクタの構成別にJISで規定されており、プラグ対プラグ(光接続コード)のときの基準試験方法は、挿入法(C)である(令和3年2回)。⇒現行のJISに基づくと、挿入法(B)が正解となります。
※以前は測定法についてJIS C 5961とJIS C 61300があり、過去問ではJIS C 5961に基づく出題がなされていました(令和3年第2回等)。現在はJIS C 5961は廃止され、JIS C 61300に統合されています。過去問に取り組む際は現在のものと答えが変わる可能性がありますのでご注意ください。
以下、現行のJIS規格について記載いたします。
(JIS C 61300-3-4:2017より抜粋)
| 供試品の端子の形態 | 基準測定法 | 代替測定法 |
| 光ファイバ対光ファイバ(光受動部品) | カットバック | OTDR |
| 光ファイバ対光ファイバ(融着または現場取付形光コネクタ) | 挿入(A) | カットバックまたはOTDR |
| 光ファイバ対プラグ | カットバック | OTDR |
| プラグ対プラグ(光受動部品) | 挿入(B) | 挿入(C)、置換またはOTDR |
| プラグ対プラグ(光パッチコード) | 挿入(B) | 挿入(C)、置換またはOTDR |
| 片端プラグ(ピッグテール) | 挿入(B) | OTDR |
| レセプタクル対レセプタクル(光受動部品) | 挿入(C) | 置換またはOTDR |
| レセプタクル対プラグ(光受動部品) | 挿入(C) | 置換またはOTDR |
代替測定法よりも、基準測定法の方が出題可能性が高いと推測します。基準測定法を優先的に覚えていただければと思います。
【JIS規格と工事担任者試験の出題について思うこと】
JIS C 5961(光ファイバコネクタの試験方法に関する規格)は、2019年の段階で将来的な廃止が予定されており、その後、2020年正式に廃止されました。
以降は、JIS C 61300シリーズに統合されて運用されています。
この動きを受けて、私は2019年5月23日公開のYouTube動画において、
JIS C 61300に基づいた解説を行いました。
また、同年に出版した書籍でも、最新のJIS(C 61300)に基づいて執筆しています。
これは当時の私にとっても非常に悩ましい判断でしたが、
「正しい情報を届けたい」という一心で、最新規格準拠で掲載することを決断しました。
ところがその後、令和3年(2021年)第2回の工事担任者試験(総合通信)において、
すでに廃止されていたJIS C 5961に基づく出題がなされました。
当然ながら、私の書籍で学習された方は、
「最新の正しい知識を持っているのに正解できない」という、極めて理不尽な状況に置かれてしまいました。
さらに翌年の令和4年(2022年)第1回(第1級デジタル)でも、
再びJIS C 5961ベースの出題が確認されています。
試験問題の文面では「JISで規定されており」とだけ書かれており、
どのJISに基づいているのかが明示されていません。
このような状況では、受験生は「過去に出題された問題」だけを頼りにするしかないというのが現実です。
こうした経緯を踏まえ、以降に制作した参考書(改訂版)では、
過去に実際に出題された内容を基準に掲載する方針へと切り替えました。
この判断もまた、悩みに悩んだ末のものでした。
近年では、他社から出版されている教材の多くも、
JIS C 61300に基づいた記述が主流となってきています。
中には、令和4年(2022年)第1回試験の設問をJIS C 61300ベースに改題したうえで収録している書籍も見られます。
このような動向を受けて私も、
「今後出題されるのであれば、JIS C 61300に基づくものであるべきだ」と考え、
今回あらためてこの情報を公開するに至りました。
とはいえ、過去に“正しい知識”で学習した受験生が不当に失点してしまった経験は、
今でも私の中で小さくないトラウマとして残っています。
そのため、今もどこか不安や複雑な思いを拭いきれないというのが正直なところです。
ここからは、私個人の見解です。
- もし今回(2025年試験)でJIS C 61300に基づいた出題がなされれば、
→ 過去の2021年・2022年の出題は、実質的に限りなく出題ミスに近いものだったのではないか。 - 逆に、今回もなおJIS C 5961に基づく出題がなされるならば、
→ すでに正式に廃止された規格に基づいて出題していることとなり、
やはり出題ミスの可能性があるのではないかと感じています。
いずれにしても、出題者側にはぜひ次の点をお願いしたいと考えています。
📌 「どのJISに基づいて出題しているのか」を、問題文や受験案内などに明記していただきたい。
📌 受験生がどの規格に基づいて勉強すればよいのか、明確な指針を示していただきたい。
これは、日々不安を抱えながらも真剣に学習に取り組んでいる受験生たちの努力を守るために、
必要不可欠な配慮であると私は強く感じています。
つらつらと愚痴のようになってしまったかもしれませんが、
私はただ、受験生の皆さんが正しい努力で、1点でも多く得点できるようにと心から願っています。
どうか皆さまの努力が報われますように。
あなた様の合格を、陰ながら心よりお祈り申し上げます。