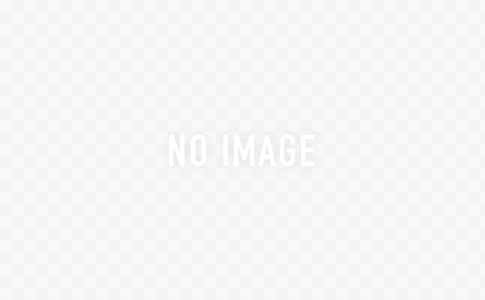「端末設備等規則」関連で法改正が多く行われており、本書の内容と齟齬が生じております。読者の皆様には度々ご不便をおかけし、重ねてお詫び申し上げます。以下、全てを列挙することは困難であるため、本書に記載の部分に限り、変更箇所を列挙させていただきます。
<追記修正あり!>「端末設備等規則」に間しては、総務省告示第357号の規定により、実質変化なしとなります。 以下、項目名の横に★印で変更あり、なしを記載します。 また、下記記事内容に関して解説動画をご用意いたしました。(最終編集日時:2025年5月24日20:55)
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 ★重要変更あり 本書P276
技術基準適合認定番号等の最初の文字に関して、次表が法改正後のものとなります。
| 端末機器の種類 | 記号 |
| 固定電話端末 | G |
| インターネットプロトコル移動電話端末 | H |
| 専用通信回線設備等端末 | P |
| 以下の端末機器 ・移動電話用設備に接続される端末機器(インターネットプロトコル移動電話端末を除く) ・無線呼出用設備に接続される端末機器 | Q |
端末設備等規則 ★軽微な変更あり
法文削除等ありましたが、別途告示(総務省告示第357号)が設けられおり、実質上の変化は軽微なものでした。一部、「インターネットプロトコル電話端末」が「固定電話端末」に変わる等があります。
定義 (本書P279-282)
法文上は、二、三、十二、十三、二十が削除となっておりましたが、別途総務省告示第357号等にて同様の規定が設けられているため、実質的な変化は軽微なものとなります。以下、本書掲載範囲にて、変更が発生した箇所を黄色マーカで示します。
一 「電話用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
二 「アナログ電話用設備」とは、電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点においてアナログ信号を入出力とするものをいう。※総務省告示第357号
三 「アナログ電話端末等」とは、端末設備であって、アナログ電話用設備に接続される点において二線式の接続形式で接続されるものをいう。※総務省告示第357号
四 「移動電話用設備」とは、電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう。
五 「移動電話端末」とは、端末設備であって、移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。)に接続されるものをいう。
六 「固定電話用設備」とは、電話用設備であって、電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して提供する音声伝送役務の用に供するものをいう。
七 「固定電話端末」とは、端末設備であって、固定電話用設備に接続されるものをいう。
八 「インターネットプロトコル移動電話用設備」とは、移動電話用設備(電気通信番号規則別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用して提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。
九 「インターネットプロトコル移動電話端末」とは、端末設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものをいう。
十 「無線呼出用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、無線によつて利用者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。)を行うことを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
十一 「無線呼出端末」とは、端末設備であつて、無線呼出用設備に接続されるものをいう。
十二「総合デジタル通信用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の提供の用に供するものをいう。※事業用電気通信設備規則第三条二項五号
※告示第357号には、「総合デジタル通信用設備」という文言が記載されていないため、この用語の定義は削除されたものと推察されます(私見) →事業用電気通信設備規則第三条二項五号にて、「総合デジタル通信用設備」の定義があることを発見しました。この法令自体は工事担任者試験の範囲外の可能性がありますが、電気通信事業法施行規則がこの条文をリファレンスしていることから、出題の可能性はありうると判断します(つまり、今まで通り)。二転三転し、申し訳ございません。
十三 「総合デジタル通信端末等」固定電話端末等であって、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換する事業用電気通信設備に接続されるものをいう。※総務省告示第357号
十四 「専用通信回線設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。
十五 「デジタルデータ伝送用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により、専ら符号又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
十六 「専用通信回線設備等端末」とは、端末設備であって、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続されるものをいう。
十七 「発信」とは、通信を行う相手を呼び出すための動作をいう。
十八 「応答」とは、電気通信回線からの呼出しに応ずるための動作をいう。
十九 「選択信号」とは、主として相手の端末設備を指定するために使用する信号をいう。
二十 「直流回路」とは、電気通信回線設備に接続して電気通信事業者の交換設備の動作の開始及び終了の制御を行うための回路をいう。※総務省告示第357号
二十一 「絶対レベル」とは、一の皮相電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。
二十二 「通話チャネル」とは、移動電話用設備と移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話端末の間に設定され、主として音声の伝送に使用する通信路をいう。
二十三 「制御チャネル」とは、移動電話用設備と移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話端末の間に設定され、主として制御信号の伝送に使用する通信路をいう。
二十四 「呼設定用メッセージ」とは、呼設定メッセージ又は応答メッセージをいう。
二十五 「呼切断用メッセージ」とは、切断メッセージ、解放メッセージ又は解放完了メッセージをいう。
実質的な定義の変更があったところには黄マーカーを記しております。
なお、法令上削除されたところは、代わりに「総務省告示第357号」等の規定があるため、実質変化なし。
絶縁抵抗等 (本書P283) ★重要変更あり
法改正後は次のとおりです。
第六条 端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に次の絶縁抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。
一 絶縁抵抗は、使用電圧が250ボルト以下の場合にあつては、2メガオーム以上であること。
二 絶縁耐力は、使用電圧が250ボルトを超える場合にあつては、2,500ボルトの電圧を連続して1分間加えたときこれに耐えること。
2 端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が100オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあっては、この限りでない。
その他変更点 ★軽微な変更あり
その他変更点に関して下記列挙させていただきます。
・アナログ電話端末に関する規則
該当条文「端末設備等規則」第十条~第十六条→削除
代わりに、「総務省告示第357号」の規定により、実質変化なし。
・総合デジタル通信用設備に接続される端末設備
該当条文「端末設備等規則」第三十四条の二~第三十四条の七→削除
代わりに、「総務省告示第357号」の規定により、実質変化なし。
・第三節 インターネットプロトコル電話端末
■該当条文 第三十二条の二~第三十二条の九→「インターネットプロトコル」を「固定」に読み替え
例:インターネットプロトコル電話端末→固定電話端末
■第三十二条の八
旧:インターネットプロトコル電話端末がアナログ電話端末等と通信する場合にあつては、通話の用に供する場合を除き、インターネットプロトコル電話用設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、別表第五号のとおりとする。
→新:固定電話端末の送出電力は、通話の用に供する場合を除き、別表第五号のとおりとする。
上記2点、本書P291-P292が該当箇所となります。